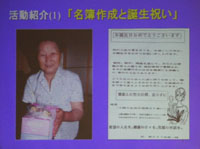2008年11月26日
コンテンツ番号2623
心の健康づくりで自殺予防を
(2008.11.26)

講師の秋田大学医学部・湯浅孝男教授(26日、北秋田市保健センターで)
「高齢者の自殺をなくそう!!〜鷹巣阿仁地域自殺予防の集い」が11月26日(水)、北秋田市保健センターで開かれ、約100人の参加者が、心の健康についての講演や、精神保健ボランティア、生きがいづくりについての活動発表を聴き、自殺予防への理解を深めました。
北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部と鷹巣阿仁地域自殺予防ネットワーク会議の主催。はじめに、鷹巣阿仁福祉環境部の豊島優人部長が、秋田県や鷹巣阿仁地域の自殺の現状などに触れ、「管内の平成19年中の自殺者は15人。自殺による死亡率は平成11年を最高に徐々に低下しているが、秋田県の自殺率は依然として全国でトップ。県でもさまざまな取り組みを進めているが、まずは一人ひとりが正しい知識を持ち、できることから取り組むことが大切」、などとあいさつ。
続いて、秋田大学医学部保健学科の湯浅孝男教授が、「高齢者の自殺を防ぐために〜こころの健康づくり」と題して講演。また、精神保健福祉ボランティアれもんの会代表の小坂和子さんと北秋田市老人クラブ道城希望会の津幡保三会長がそれぞれ会の取り組について発表しました。
講演では、湯浅教授が自殺に至る動機や心の動き、自殺者の思考法、高齢者のうつ病の特徴などについて説明しました。「誰でも悩みや不安を持つが、心が健康なときは『周囲に迷惑をかける』『自殺はいけない』などとの認識があり、また解決策を考えられる。しかし自殺に至る多くのケースでは、心理的に視野が狭くなっており健康なときのような思考ができなくなっている。健康な人の視点で話をしても逆効果」と、まずよく話を聴くことが理解につながると話しました。
また、こういった心理状況は特にうつ病で多く見られ、60歳以上の高齢者の7人に1人、約15%が病気一歩手前の「うつ状態」で、そのうち5%がうつ病であることを紹介。「うつ病は『心の風邪』。風邪が悪化すると命取りになる。怖いのはうつ病になることではなく、病気を見逃し何も手を打たないこと」と、周囲がその兆候に早く気づき、ことばをかけてあげることの大切さを述べました。
高齢者のうつ病の特徴として、抑うつなどのうつ病の典型的な症状よりも、胃腸の働きがよくない、食欲がないなどの身体的な訴えが多いそうです。
「死」を口にされたときの対応としては、「『死にたい』『助けてほしい』の葛藤から出た言葉。辛い話題だが、話をそらしたり、一方的に話す、また常識を述べ説得することはしてはならない。真剣に耳を傾け、共感してあげることが大切」、と対応法を説明しました。
この後、れもんの会の小坂代表と道城希望会の津幡会長が活動発表を行いました。このうち津幡会長は、道城集落での生きがいづくりについての取り組みを紹介。▽老人クラブ全員の誕生日の名簿を作成し、誕生日に贈り物を届ける▽健康増進と世代間交流を目的にソバづくり▽環境美化を目的に市道沿いにひまわりを植栽▽七夕火祭りの実施、などの取り組みを通じ、高齢者一人ひとりが地域の中で役割を持ち支えあうことで、生きがいを感ずるようになり自殺予防にもつながることを紹介。
最後に、「動ける人は人のために働き、動けなくなったら人から感謝されるような老人になることが理想。やさしさと真心で人に接し、尊敬と感謝、奉仕の心を知ることが心の健康づくりにつながる」と、会場に語りかけていました。